共同研究について
民間企業等から研究者(共同研究員)及び研究経費等を受け入れて、本校教職員が共同研究員と共通のテーマについて共同して行う研究です。
また、民間企業等と本校がそれぞれの施設で分担して研究を行うこともできます。
研究員の派遣
民間企業等の研究者が本校において研究に従事する場合には、研究料として一人につき年額42万円の経費が必要になります。
申込み方法
共同研究のお申し込みは、本校所定の「共同研究申込書」をご提出ください。
申込みをいただきますと、共同研究の受諾を行い、契約を締結します。
この契約の完了を受け、研究料と研究経費を納入していただくことになり、その後に、研究(含む研究員の受入れ)を開始します。
従いまして、お申込み後、研究開始までの間、契約手続き等のための日数が必要になりますので、期間の余裕を見てお申し込みください。
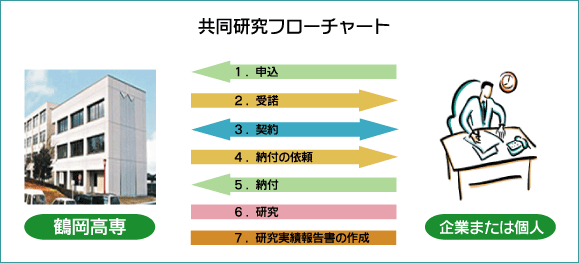 |
複数年契約
複数年継続する共同研究を行うことも可能です。
複数年の研究期間を設定する場合には、お申し込み時に経費の負担等も含め、契約期間の設定について、ご相談させていただきます。
特許等の取扱い
創造された発明に対する寄与の程度を基礎に、本校の教職員と企業との間のパートナーシップを尊重し、特許等の帰属を高専機構になるか発明教職員個人になるかを個別に判断します。その上で、権利の持分、優先的実施権の設定、出願等に係る経費の負担について、ケース・バイ・ケースで協議により決定します。
税の優遇措置
共同研究のために支出した経費の一定割合については、法人税や所得税から控除される税制上の優遇措置があります。
共同研究実績報告書
共同研究終了後に、共同研究者双方が協力し、共同研究実施期間中に得られた研究成果を研究実績報告書として纏めていただくことになります。
研究紹介
最近5年間の実績
1.最近5年間(令和元年度~令和5年度)に本校で実施された共同研究の件数は、次のとおり。
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 件数 | 20 | 21 | 22 | 18 | 17 |
2.最近5年間に実施された共同研究の具体的な内容は次のとおり。
令和5年度
| 担当教員 | 所属 | 共同研究機関等 | 研 究 テ - マ |
| 岩岡 伸之 | 機械コース | 県外企業 | エラストマー材料に関する研究 |
| 森永 隆志 佐藤 涼 |
化学・生物コース 化学・生物コース |
県内企業 | 構造タンパク質を用いたブロック共重合体分析評価方法 |
| 上條 利夫 | 化学・生物コース | 県外公的機関 | 滑雪コーティング技術開発に向けたイオンブラシ材料特性評価の検証 |
| 神田 和也 伊藤 卓朗 |
電気・電子コース 基盤教育グループ |
山形大学・県内企業 | 低消費小型AIデバイスを活用した社会実装に向けた研究 |
| 遠藤 大希 | 機械コース | 県内団体 | 海洋ゴミのアップサイクルに適した機械製作に関する研究 |
| 和田 真人 | 機械コース | 県内企業 | 高専デジタルファブリケーションによる技術教育の場の創出 |
| 吉木 宏之 遠田 明広 |
機械コース 教育研究技術支援センター |
県外企業 | 1.4-ジオキサン(DXA)および有害物質等の分解法の研究 |
| 金 帝演 | 情報コース | 県内企業 | AI画像処理システムの研究 |
| 久保 響子 | 化学・生物コース | 長岡技術科学大学 | 海洋細菌のケミカルリサイクルへの利用可能性評価 |
| 伊藤 滋啓 | 化学・生物コース | 長岡技術科学大学 | 窒素ドープグラフェンカソード(rGO-N)表面の格子酸素減少によるPEFC燃料電池性能の改善効果 |
| 森谷 克彦 宝賀 剛 田中 勝 |
電気・電子コース 電気・電子コース 電気・電子コース |
長岡技術科学大学 | 太陽電池に関する共同研究を通じた高専教育の充実と研究を継続できる環境の構築 |
| 南 淳 | 化学・生物コース | 長岡技術科学大学 | 森林性クローナル植物ヤブコウジのクローン集団の変遷とエピジェネティクス |
| 櫻庭 崇紘 | 電気・電子コース | 豊橋技術科学大学 | 草刈りおよび滞水除去機能を有するグラウンド整備ロボットの開発 |
| 宍戸 道明 | 機械コース | 豊橋技術科学大学 | 非拘束環境下における睡眠障害の状態監視およびアプニア検出 |
| 小寺 喬之 | 化学・生物コース | 県外企業 | 噴霧熱分解法によるリン酸鉄リチウム正極材料に関する研究 |
| 宝賀 剛 | 電気・電子コース | 県外企業 | 松枯れ防止装置の製作および効果実証に関する研究 |
| 小寺 喬之 | 化学・生物コース | 県外企業 | タイヤ由来熱分解物の用途開発に関する粒子特性調査研究 |
令和4年度
| 担当教員 | 所属 | 共同研究機関等 | 研 究 テ - マ |
| 斎藤 菜摘 | 化学・生物コース | 長岡技術科学大学 | 酵素機能および二次代謝物質に関する研究 |
| 五十嵐幸德 | 機械コース | 長岡技術科学大学 | MAX相セラミックスおよび高融点シリサイド密体作成と機械的特性評価 |
| 白砂 絹和 | 機械コース | 豊橋技術科学大学 | 睡眠中の呼吸数カウントデバイスの開発とその解析 |
| 櫻庭 崇紘 | 電気・電子コース | 豊橋技術科学大学 | 産業機械駆動装置の設計と制御 |
| 伊藤 卓朗 神田 和也 金 帝演 |
基盤教育グループ 電気・電子コース 情報コース |
山形大学・県内企業 |
鴨生産モデルの立ち上げ |
| 上條 利夫 森永 隆志 荒船 博之 伊藤 滋啓 遠藤 博寿 |
化学・生物コース 化学・生物コース 機械コース 化学・生物コース 化学・生物コース |
県外公的機関 | 滑雪コーティング技術開発に向けたイオンブラシ材料特性評価の検証 |
| ザ ビ ル 保科紳一郎 高橋 淳 |
情報コース 電気・電子コース 電気・電子コース |
県外企業 |
日本型高専教育手法による技術者教育の国際標準モデルの研究 |
| 森永 隆志 佐藤 涼 |
化学・生物コース 化学・生物コース |
県内企業 | 構造タンパク質を用いたブロック共重合体の開発及び分析評価方法 |
| 吉木 宏之 | 機械コース | 県外企業 | 1.4-ジオキサン(DXA)および有害物質等の分解法の研究 |
| 保科紳一郎 | 電気・電子コース | 県外公的機関 | 積雪の通気度の自動計測装置の開発研究 |
| 櫻庭 崇紘 | 電気・電子コース | 県外企業 | 地震感知器に関する研究 |
| 本橋 元 | 機械コース | 県内企業 | 除塵機能付き小水力発電取水器の性能評価 |
| 本橋 元 | 機械コース | 県外企業 | オルタネータの出力特性試験の研究 |
| 和田 真人 | 機械コース | 県内企業 | 高専デジタルファブリケーションによる技術教育の場の創出 |
| 和田 真人 | 機械コース | 県内企業 | 高精度薄物切削加工の技術開発 |
| 遠藤 大希 | 機械コース | 県外企業 | 空中風力発電実験に伴う評価 |
| 和田 真人 | 機械コース | 県内企業・県外企業 | 人協働ロボットを活用したデジタル学習教材に関する研究 |
| 遠藤 博寿 | 化学・生物コース | 県外企業 | 円石藻の遺伝子解析とゲノム編集の検討 |
令和3年度
| 担当教員 | 所属 | 共同研究機関等 | 研 究 テ - マ |
| 金 帝演 | 情報コース | 県外公的機関 | モビリティロボットの安全性及びナビゲーションに関する研究 |
|
神田 和也 |
電気・電子コース 電気・電子コース 情報コース |
県内団体 | 簡易ウェザーステーションの開発と実証試験 |
| 岩岡 伸之 | 機械コース | 県外企業 | エラストマー材料に関する研究 |
| 荒船 博之 上條 利夫 |
機械コース 化学・生物コース |
県外企業 | マルチブロックコポリマーの自己修復機能発現とトライボロジー応用 |
| 森永 隆志 伊藤 滋啓 |
化学・生物コース 化学・生物コース |
県外企業 | 新規アイオノマーに関する研究 |
| 森永 隆志 | 化学・生物コース | 海外企業 | 固体ゲル電解質の開発と改良研究 |
| 森永 隆志 伊藤 滋啓 |
化学・生物コース 化学・生物コース |
県外公的機関 | 高性能酸化物形燃料電池デバイスの作成 |
| 保科紳一郎 高橋 淳 ザ ビ ル |
電気・電子コース 電気・電子コース 情報コース |
県外企業 | 日本型高専教育手法による技術者教育の国際標準モデルの研究 |
| 森永 隆志 佐藤 涼 |
化学・生物コース 化学・生物コース |
地元企業 | 構造タンパク質を用いたブロック共重合体の開発 |
| 吉木 宏之 遠田 明広 |
機械コース 教育研究技術支援センター |
県外企業 | 1,4-ジオキサン(DXA)およびテトラクロロエチレン(PCE)分解法の研究 |
| 斎藤 菜摘 | 化学・生物コース | 慶應義塾大学 | 次世代食糧供給に向けた技術開発 |
| 久保 響子 斎藤 菜摘 |
化学・生物コース 化学・生物コース |
長岡技術科学大学 | 海洋性細菌の多様性と分離培養 |
| 森谷 克彦 宝賀 剛 髙橋 聡 |
電気・電子コース 電気・電子コース 情報コース |
長岡技術科学大学 | 環境調和型薄膜太陽電池の開発を通じた高専-技大研究ネットワークの形成 |
| 五十嵐幸徳 | 機械コース | 長岡技術科学大学 | 高融点シリサイドおよびセラミックスの作製 |
| 白砂 絹和 | 機械コース | 豊橋技術科学大学 | 小児起立性調節障害の診断支援 |
| 斎藤 菜摘 | 化学・生物コース | 地元企業 | 微生物培養法の開発 |
| 伊藤 卓朗 | 基盤教育グループ | 東京大学 県外企業 |
優れた酵母の分取または創出とそれを用いたビールの実現 |
| 佐藤 貴哉 荒船 博之 上條 利夫 森永 隆志 伊藤 滋啓 佐藤 涼 森木 三穂 |
機械コース 化学・生物コース 化学・生物コース 化学・生物コース 化学・生物コース 基盤教育グループ |
県外公的機関 | 滑雪コーティング技術の社会実装に向けた社会科学的調査研究 |
| 神田 和也 | 電気・電子コース | 地元企業 | ぶどう栽培に関する生育環境データ取得および分析の研究 |
| 白砂 絹和 | 機械コース | 地元企業 | 機械学習・深層学習の活用に関する研究 |
| 宍戸 道明 佐藤 司 伊藤 眞子 |
情報コース 化学・生物コース 教育研究技術支援センター |
地元企業 | フェノール樹脂廃棄物再利用に関する研究 |
| 伊藤 卓朗 | 基盤教育グループ | 慶應義塾大学 | ヤマブドウ樹液のメタボローム解析 |
令和2年度
| 担当教員 | 所属 | 共同研究機関等 | 研 究 テ - マ |
| 金 帝演 | 情報コース | 県外公的機関 | 安全性及びナビゲーションに関する研究 |
| 矢吹 益久 保科紳一郎 一条 洋和 |
機械コース 電気・電子コース 教育研究技術支援センター |
県外公的機関 | 簡易水位計の開発 |
| 岩岡 伸之 | 機械コース | 県外企業 | 分子シミュレーションの研究 |
| 神田 和也 金 帝演 |
電気・電子コース 情報コース |
県内団体 | 簡易ウェザーステーションの開発と実証試験 |
| 佐藤 貴哉 森永 隆志 上條 利夫 |
化学・生物コース 化学・生物コース |
県外企業 | イオン液体のプロトン伝導生、酸素透過性に関する研究 |
| 荒船 博之 上條 利夫 |
機械コース 化学・生物コース |
県外企業 | 自己修復機能発現とトライボロジー応用 |
| 森永 隆志 伊藤 滋啓 |
化学・生物コース 化学・生物コース |
県外企業 | 新規アイオノマーに関する研究 |
| 森永 隆志 | 化学・生物コース | 地元企業 | 組換え構造タンパク質及び成形体の製造方法 |
| 構造タンパク質材料の新規分離精製技術の開発 | |||
| 佐藤 司 | 化学・生物コース | 地元企業 | FRP廃棄物の有効利用に関する研究 |
| 岩岡 伸之 | 機械コース | 県外企業 | エラストマー材料に関する研究 |
| 吉木 宏之 遠田 明広 |
電気・電子コース 教育研究技術支援センター |
県外企業 | マイクロバブル―プラズマを用いた分解法の研究 |
| 佐藤 貴哉 上條 利夫 |
化学・生物コース | 県内企業 | 高機能性布マスクの性能評価 |
| 和田 真人 | 機械コース | 県内企業 | フェイスシールドの研究開発 |
| 伊藤 滋啓 正村 亮 |
化学・生物コース 電気・電子コース |
長岡技術科学大学 | 新規リチウムイオン電導固体電解質の合成と材料設計 |
| 久保 響子 斎藤 菜摘 |
化学・生物コース 化学・生物コース |
長岡技術科学大学 | 簡便な分離培養法の確立と単離 |
| 安田 新 森谷 克彦 |
情報コース 電気・電子コース |
長岡技術科学大学 | 太陽電池化合物材料の画期的な物性評価方法の提案 |
| 阿部 達雄 | 化学・生物コース | 長岡技術科学大学 | 生態影響評価と相互作用 |
| 髙橋 聡 | 情報コース | 豊橋技術科学大学 | センシングシステムの検討 |
| 森木 三穂 | 基盤教育グループ | 地元企業 | 管楽器奏者用フェイスシールドの研究開発 |
| 森永 隆志 | 化学・生物コース | 海外企業 | 固体ゲル電解質の開発と改良研究 |
平成31年度(令和元年度)
| 担当教員 | 所属 | 共同研究機関等 | 研 究 テ - マ |
| 金 帝演 | 情報コース | 県外公的機関 | 安全性及びナビゲーションに関する研究 |
| 中山 敏男 | 情報コース | 県外企業 | 内視鏡に関する研究開発 |
| 矢吹 益久 保科紳一郎 一条 洋和 |
機械コース 電気・電子コース 教育研究技術支援センター |
県外公的機関 | 簡易水位計の開発 |
| 佐藤 貴哉 上條 利夫 |
化学・生物コース | 県外企業 | 燃料電池用固体電解質の開発 |
| 上條 利夫 | 化学・生物コース | 地元企業 | シャフト摩耗の原因調査のための基礎研究 |
| 神田 和也 | 電気・電子コース | 地元企業 | ウェザーステーション活用の可能性検証 |
| 安田 新 森谷 克彦 髙橋 聡 |
情報コース 電気・電子コース 情報コース |
東北大学 | テラヘルツ分光測定による物性評価 |
| 岩岡 伸之 | 機械コース | 県外企業 | 分子シミュレーションの研究 |
| 神田 和也 金 帝演 |
電気・電子コース 情報コース |
県内団体 | 簡易ウェザーステーションの開発と実証試験 |
| 佐藤 貴哉 森永 隆志 上條 利夫 |
化学・生物コース 化学・生物コース |
県外企業 | イオン液体のプロトン伝導生、酸素透過性に関する研究 |
| 吉木 宏之 | 電気・電子コース | 県外企業 | 1,4ージオキサン(DXA)およびテトラクロロエチレン(PCE)分解法の研究 |
| 佐藤 貴哉 | 県外企業 | レジリエンシー強化とトライボロジー応用(ACCELプログラム) | |
| 小寺 喬之 矢作 友弘 |
化学・生物コース 教育研究技術支援センター |
県外企業 | 微粒子製造技術の基礎的検討 |
| 佐藤 司 松浦由美子 伊藤 眞子 |
化学・生物コース 化学・生物コース 教育研究技術支援センター |
地元企業 | 木質燃料焼却灰を利用した再生骨材(BRC)の開発 |
| 森永 隆志 | 化学・生物コース | 地元企業 | 組換え構造タンパク質の製造方法及び成形体の製造方法 |
| 斎藤 菜摘 | 化学・生物コース | 長岡技術科学大学 | KOSEN-GIGAKUジョイント高専生サミットon Science and Technology |
| 森谷 克彦 安田 新 宝賀 剛 |
電気・電子コース 情報コース 電気・電子コース |
長岡技術科学大学 | テラヘルツ分光測定による物性評価とデータベース化 |
| 南 淳 | 化学・生物コース | 長岡技術科学大学 | DNAメチル化多型の要因 |
| 飯島 正雄 | 化学・生物コース | 地元企業 | ニラ香気吸着研究[予備試験1] |
| 佐藤 司 | 化学・生物コース | 地元企業 | FRP廃棄物の有効利用に関する研究 |
共同研究に関するお問合せはこちらへ
| 総務課企画・連携係 | |
| 電話: | 0235-25-9453/9159 |
| FAX: | 0235-24-1840 |
| 住所: | 〒997-8511 山形県鶴岡市井岡字沢田104 |
| Mail: | kikaku@ ※@以降に「tsuruoka-nct.ac.jp」とご入力ください。 |
| 直接各研究者にお問い合わせいただいても結構です。その場合は各研究(シーズ)紹介ページに掲載のe-mailをご利用ください。但しe-mailアドレスの@以降に「tsuruoka-nct.ac.jp」とご入力ください。 | |
