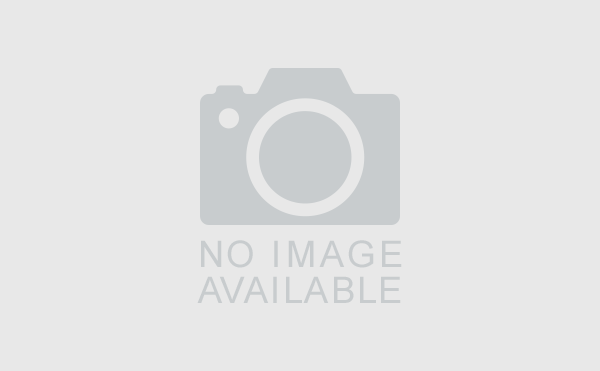令和2年度社会実装教育フォーラムで、本校参加チームが「構想賞」を受賞しました
令和3年3月5日(金)~3月6日(土)にかけて開催された令和2年度社会実装教育フォーラムにおいて、本校学生の齋藤 穣さん、佐藤博史さん(化学・生物コース4年)、上林未来人さん(機械コース4年)、阿部 開さん(化学・生物コース3年)が「構想賞」を受賞いたしました。
社会実装教育とは、学生が仲間と互いの強みを活かしつつ、実際に関わる企業やユーザーとともに現実の課題解決を目指すものです。社会実装教育フォーラムは、学生が課題解決に取り組み、その成果を発表するだけでなく、専門家である審査員から的確な評価を得る場として、東京高専の主催で例年この時期に開催されております。今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、オンライン形式での開催となりました。
受賞テーマは、「障害者のディーセントワークを図る簡易紙漉き装置の開発」です。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、多くの福祉施設から、障がいのある方が製作した商品の販売に苦慮しており、入所している方々が落胆しているとのお話を伺った4名の学生は、障がいのある方々が誇りをもった仕事(ディーセントワーク)をできるよう、地元鶴岡市の観光地である月山高原のひまわり畑で収穫される葉を原料として「月山高原ひまわり紙」を作ろうと考えました。この「月山高原ひまわり紙」は和紙であるため、製作には熟練の技が必要ですが、4名の学生は「簡易紙漉き器」を開発することで、特別な技術がなくても作れるよう、何度も試作を重ねました。
結果として、この紙漉き器を使用して製作した紙は少し固く、和紙としてではなくコースターとして活用することとなりましたが、設定した社会課題やその解決に向けた構想が高く評価され、今回受賞のはこびとなりました。
オンラインでの開催となったことにより、今回は対面での発表とは異なる苦労も多々ありました。特に、応募する際に提出した動画の撮影では、80秒以内という制約があったことから、納得のいくまで何度も何度も撮影したそうです。「今後はより柔らかい紙ができるよう、紙漉き器をさらに改良していきたい」と話す4名の皆さんに、これからもご期待ください。
 |
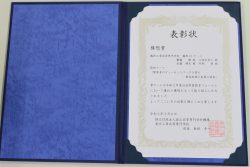 |
| 受賞した4名の学生(左から齋藤さん、佐藤さん、上林さん、阿部さん) | |