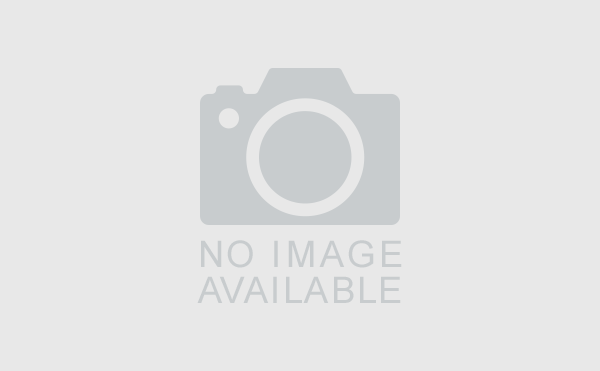研究成果の論文が、米国の学術論文雑誌ACS Applied Energy Materials(2019年07月29日付)に掲載されました
鶴岡工業高等専門学校 創造工学科 化学・生物コースの伊藤滋啓准教授(筆頭著者)、佐藤貴哉教授らによる論文:「Design of active site at hetero-interface between brownmillerite type oxide promoter and fluorite cubic ZrO2 in anode of intermediate temperature SOFCs」が、米国の学術論文雑誌ACS Applied Energy Materials(2019年07月29日付)に掲載されました。
この論文では、伊藤准教授らがオリジナルに開発した混合伝導体酸化物BIZZOを固体酸化物形燃料電池(SOFC)のアノード助触媒として使用することで、アノード層内に反応活性サイトを形成し性能を向上させ、またBIZZO助触媒を添加することで長時間安定性を可能にすることを明らかにしたことが報告されています。
(論文は、下記のURLにで、どなたも概要が無料で読むことが可能です)
■全著者:Shigeharu ITO, Toshiyuki Mori, Akira Suzuki, Hiroshi Okubo, Shunya Yamamoto, Takaya Sato, Fei Ye
■URL https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsaem.9b00864
■論文の概要
固体酸化物形燃料電池(SOFC)は900~1000℃と高温作動であり、数ある燃料電池の中でも発電効率が最も高いなど多くの長所を持っている。最近では、ステンレスインターコネクターの使用が可能な中温(700℃)作動SOFCの研究開発が盛んに行われている。中温作動を可能にするため固体電解質の薄膜化について多く研究されている。
薄膜デバイス化研究では、アノード支持薄膜デバイス化が検討されている。アノード支持薄膜デバイスはアノード支持体の厚みが0.7mm程と厚くなるため電池の内部抵抗が高くなるが、NiOとYSZの最適組成を選ぶことで、活性サイト(三相界面)を、厚いアノード層内に増やすことができる。しかし、10時間以上の運転で性能低下と、水素還元による急激な性能回復が繰りかえしおこり、大きく性能が低下する。薄膜デバイス研究の場合において、性能と安定性の間のトレードオフの問題が生じる。本研究ではオリジナルの酸化物を反応活性助触媒として活用し、アノード反応高活性化・発電性能の革新的向上・性能安定性の飛躍的改善を目的とし行っており、このような取り組みを行うことで「革新的高性能と高い安定性を両立」した社会実装を目指した中温作動型安定化ジルコニア系燃料電池の創製を試みた。
解説図はこちら
用語解説:
1:混合伝導体酸化物 電子とイオンの2種類キャリア(電荷担体)を有する酸化物
2:固体酸化物形燃料電池 高温作動型の燃料電池であり高効率発電が可能
3:アノード助触媒 アノード反応を促進させるための酸化物
4:アノード層 固体酸化物燃料電池では水素が供給されて水が生成される部位
5:反応活性サイト 助触媒添加によりアノード反応が促進されるアノード内の領域
6:ステンレスインターコネクタ 燃料電池は、単体では小さな電力しか生み出せない「単セル」というものの集合体であり、燃料電池においては単セルを直列に積層あるいは連結して単セルの集合体(スタック)を構成する。この連結させる機能を担うのがインターコネクタで、ステンレス製のインターコネクタもある。